























トピックス
財団概要
梅原記念財団は、学問や芸術をとおして、社会に貢献をする一般財団法人として、平成26年、京都に設立されました。
財団の「生みの親」ともいうべき哲学者の梅原猛は、令和の時代を見ることなく、平成31年1月12日、あの世へと旅立ちました。梅原記念財団は、学問や芸術を愛した故人の遺志を偲びつつ、いろいろなかたちで、活動をしていきたいと考えています。
財団事業
梅原猛フォーラム
歴史文化の深層を探求し、人類の未来を展望した梅原哲学の検証と継承を旨に、年に一度、様々な講師を招き公開フォーラム(討論会・座談会)を開催します。
梅原猛人類哲学賞
梅原猛の営為と遺志を次代に継ぎ、人類の未来へ豊かな地平を拓く哲学探求を旨に、学術・芸術領域における画期的な取組みに対し、毎年一名(組)に授賞します。
哲学ハウス若王子
京都東山の自然に抱かれた妙喜山荘(梅原猛旧邸内)にて、「いま、これからの哲学」の探求を旨に、小規模な講演会、セミナー、勉強会などを定期的に開催します。
梅原猛
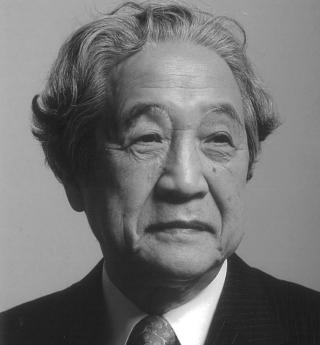
哲学者。1925年宮城県生まれ。京都大学文学部哲学科卒。立命館大学教授、京都市立芸術大学学長を経て、国際日本文化研究センターの創設に尽力し初代所長に。1999年、文化勲章を受章。縄文時代から近代までを視野に収め、文学・歴史・宗教等を包括し日本文化の深層を解明する営為が「梅原日本学」と呼ばれる。著書に『地獄の思想』『隠された十字架―法隆寺論』『水底の歌―柿本人麻呂論』『日本の深層―縄文・蝦夷文化を探る』『世阿弥の神秘』『人類哲学序説』『親鸞「四つの謎」を解く』など。1986年初演のスーパー歌舞伎「ヤマトタケル」はじめ、新たな歌舞伎・能・狂言の戯曲等も手掛け、日本ペンクラブ会長を務めた。2019年逝去。
著作
-
1965
仏像 心とかたち
-
続 仏像 心とかたち
-
1967
美と宗教の発見 創造的日本文化論
-
地獄の思想 日本精神の一系譜
-
1972
歎異抄
-
笑いの構造 感情分析の試み
-
1973
黄泉の王 私見・高松塚
-
水底の歌 柿本人麿論 上
-
水底の歌 柿本人麿論 下
-
1974
さまよえる歌集 赤人の世界
-
1976
塔
-
1977
湖の伝説 画家・三橋節子の愛と死
-
1979
歌の復籍 柿本朝臣人麿歌集論
-
学問のすすめ
-
1980
聖徳太子1 仏教の勝利
-
仏教の思想(上)
-
仏教の思想(下)
-
1981
聖徳太子2 憲法十七条
-
梅原猛著作集8 神々の流竄
-
1982
古事記
-
聖徳太子3 東アジアの嵐の中で
-
1985
聖徳太子4 理想家の孤独
-
1986
ヤマトタケル
-
1987
写楽 仮名の悲劇
-
1988
ギルガメシュ
-
日本冒険1 異界の旅へ
-
日本冒険2 太陽の輪廻
-
1989
日本冒険3 予言者の翼
-
1997
京都発見1 地霊鎮魂
-
オオクニヌシ
-
1998
京都発見2 路地遊行
-
2000
天皇家の〝ふるさと〟日向をゆく
-
脳死は本当に人の死か
-
2001
京都発見3 洛北の夢
-
2002
梅原猛の授業 仏教
-
京都発見4 丹後の鬼・カモの神
-
2003
梅原猛の授業 道徳
-
京都発見5 法然と障壁画
-
京都発見6 「ものがたり」の面影
-
2004
京都発見7 空海と真言密教
-
京都発見8 禅と室町文化
-
2006
梅原猛「神と仏」対論集 第一巻 神仏のかたち
-
梅原猛の授業 仏になろう
-
梅原猛「神と仏」対論集 第二巻 神仏のすみか
-
梅原猛「神と仏」対論集 第三巻 神仏のまねき
-
2007
京都発見9 比叡山と本願寺
-
2008
うつぼ舟Ⅰ 翁と河勝
-
2009
うつぼ舟Ⅱ 観阿弥と正成
-
2010
葬られた王朝 古代出雲の謎を解く
-
うつぼ舟Ⅲ 世阿弥の神秘
-
2012
梅原猛の授業 能を観る
-
2014
親鸞「四つの謎」を解く

